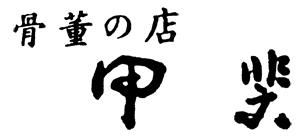2009 年 7 月 のアーカイブ
下野 八重咲き梔子
2009 年 7 月 22 日 水曜日 花 下野 八重咲き梔子
花器 鉄製農器具
日本の歴史を振り返ってみますと、鉄の農器具が生まれて飛躍的に
農産物の収穫も伸びて参ります。それとともに耕地の開墾がなされ、
それらの荘園地主である貴族が、文化の中心になり、日本人の心の
礎ともなる、文化が花開くことになります。
文章が飛躍しすぎておりますが、各自鉄文化を穴埋めして下さい。
私は山梨の農家で生まれ育ちましたので、いつも身近に鉄製農器具
がありました。それらを作業の終わった後、洗い、磨いて明日に備
える祖父や父の姿が思い出されます。
この花器に見立てた農器具は鋤簾でしょうか。
清楚で香り高い梔子の花と今を盛りと群生しています下野を活けて
みました。
梔子の良い香りが店中に満ちております。
蓮の花
2009 年 7 月 11 日 土曜日 花 蓮
花器 志野花入れ
東京の盂蘭盆会の頃になりますと、美しい蓮の花が咲きます。
普通の花屋さんでは仏前に供えるという目的だけで、葉が付い
ておりません。葉があっても、供物を包むために、茎を切り
とっております。市場でこの様にして売っておるそうです。
茶花、山野草を扱っております花屋さんでないと、花と葉を
一緒にそろえておりません。
今年は幸いにもお寺の境内に大きな鉢に幾鉢も蓮を育てており
ますのを、御住職にお願いしていただいてきました。
この、清らかな花を眼前にしておりますと、こちらの心までも
澄みゆく心地がしてまいります。
蓮の花は泥中より出でて清らかな花を咲かせるので、仏教にも
深く取り入れられております。
泥水を濁世に喩え、その中においても、心は泥に染まらず、純粋
で清らかに生きていくことを言っております。
氣の呼吸法と健康 13
2009 年 7 月 7 日 火曜日佐藤一斎著
言志四録(2)
言志後録 55 日々の心得
志気は鋭からんことを欲し、操履(そうり)は端(ただし)からんことを欲し、
品望は高からんことを欲し、識量は豁(ひろ)からんことを欲し、
造詣は深からんことを欲し、見解は実ならんことを欲す。
訳文
心の勢いは鋭くありたく、行いは端正でありたく、
品位や人望は高くありたく、見識や度量は広くありたく、
学問、技芸のきわめかたは深くありたく、ものの見方や解釈は真実でありたい。
言志後禄:全255条。佐藤一斎57歳(1828年)から67歳(1838年)までに執筆されたもの
素晴らしい言葉ですね。
読ましていただいているだけでも、背筋がすっと伸びて参ります。
いくつになっても、私たちは、素晴らしい人、言葉、文章、自然、造詣にめぐりあう
ことが出来ましたら、その時から新たな精神と肉体とを作り出すことが出来ると思います。
私もこの年齢になりまして、この様な境地を目指して 日々勤めております。
それは又喜びでも有ります。
この喜びや実践が明日への活力に繋がっているのではないかと思います。
佐藤一斎先生も日々呼吸法を実践していらっしゃいました。